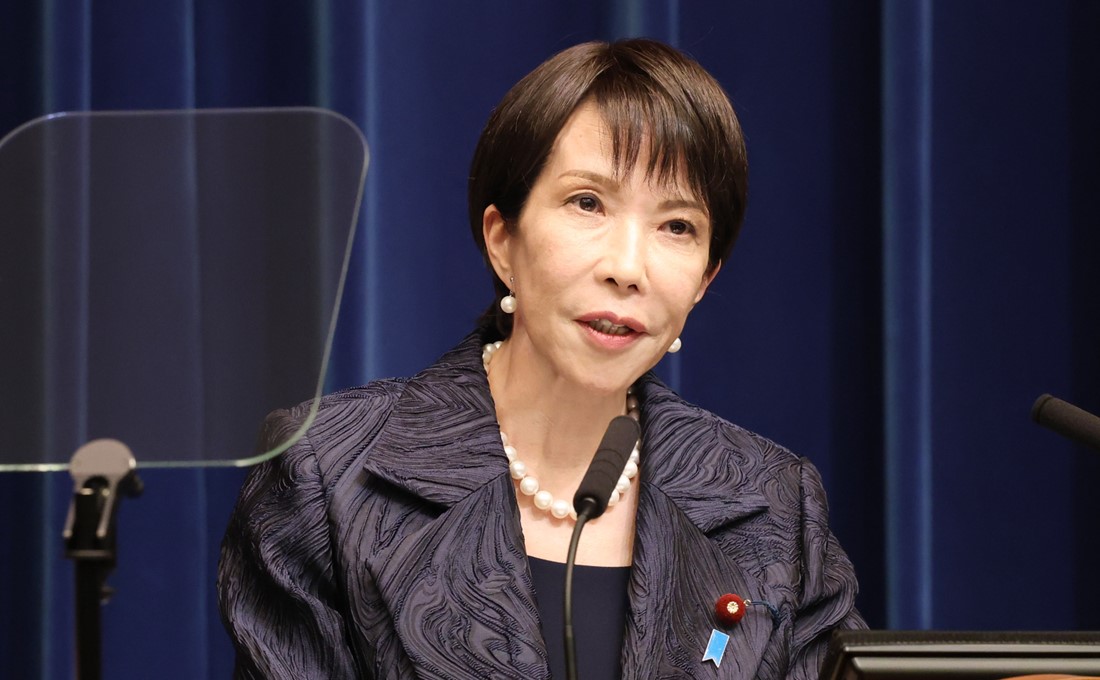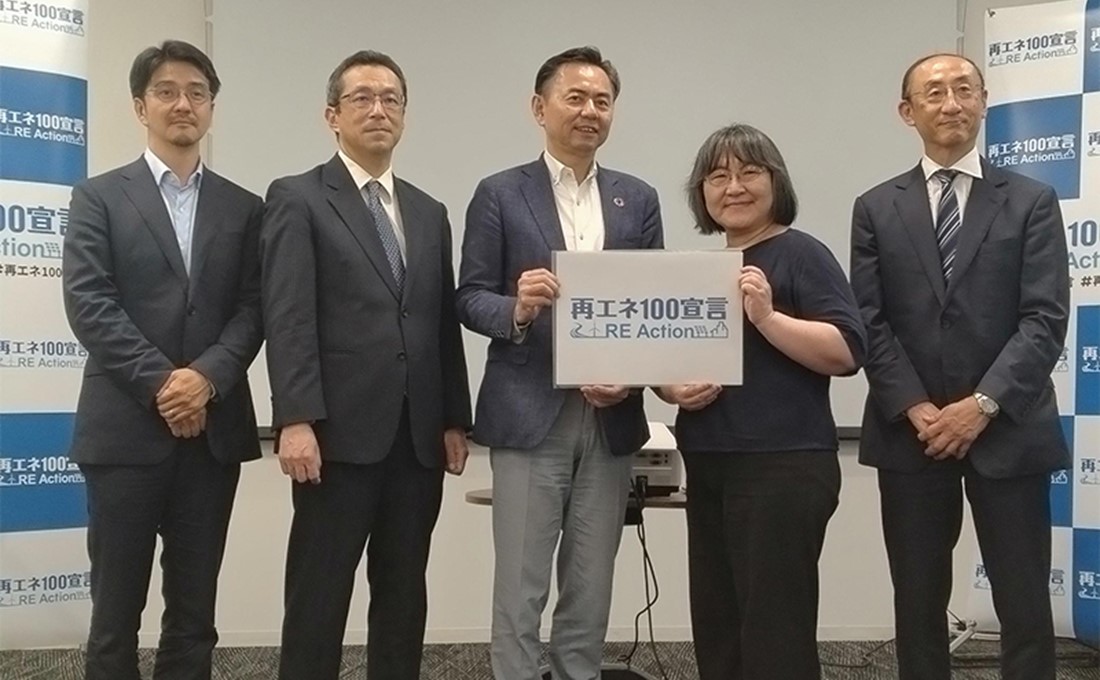ニュース
誤算もあったが…町工場、太陽光導入は「正解」と考える理
由
2025.08.26
発電した電気を工場や事務所で使う「自家消費型」太陽光発電が増えている。かつては売電が主流だったが、二酸化炭素(CO2)削減目的もあって自家消費が増えた。自家消費は電気代高騰への対抗策になる。太陽光パネルを導入した町工場を訪ねた。
補助金活用、7年で投資回収
時園製作所(埼玉県川口市)の本社は、町工場が集まった地域にある。従業員28人が働く2階建て社屋屋上に太陽光パネルが設置されている。2023年2月、発電を始めた。
近隣や地元の機械組合でも、太陽光パネルの活用は少ない。時園岳朗常務は「導入してどうかと聞かれると、必ず良かったと答えている」という。電力代が下がったからだ。
電力会社から「電気代を値上げするかもしれない」と伝えられたことがきっかけだった。同社はビールサーバーの部品を製造している。1階に並んだ旋盤やマシニングセンターが、金属から曲面のある部品を丁寧に削り出している。「機械が電気を消費しているが、ケチるわけにはいかない」(時園常務)と、太陽光発電の活用を思いついた。

ビールサーバーの部品を製造する時園製作所
インターネットで『太陽光 設置』と検索し、3社に見積もりを依頼した。そして発電量を最大限まで確保しながらも、価格が最も安い提案を選んだ。
埼玉県の補助制度を知り、申請して500万円の補助金を得られ、自己負担は約1500万円だった。申請時に優遇のある融資も紹介された。「他の補助制度に比べ、申請は手間がかからなかった」(同)という。

同社屋上の太陽光パネル(GoogleEarthから)
設置した太陽光パネル240枚の合計容量は98・4キロワット。発電した直流電気を集めて交流に変換するパワーコンディショナーの容量は49・9キロワット。つまりパネルが最大値で発電しても、工場に送る電気は半分になる。50キロワット以上だと電気主任技術者を選任して届け出るなど、コストが増えるためギリギリに抑えた。
太陽光パネルの枚数を減らしても良さそうだが、曇天や雨天でもできるだけ発電量を増やそうと多く取り付けた。もちろん、太陽光パネルだけでは必要な電気全量を賄えない。それでも発電を始めると「太陽光発電で3割を賄っているイメージ」(時園常務)という。
導入後の年間発電量は10万7000キロワット時。予測よりも2000キロワット時多かった。予想以上に電気の購入を減らせたが、誤算もあった。
工場が休みの土日は、発電した電気を売るつもりだった。この売電収入と電気代の削減効果によって7年で投資回収するはずだったが、電力会社の調整に時間がかかり、なかなか売電を始められなかった。発電開始から1年4カ月後、ようやく売電ができた。投資回収の遅れが見込まれたが、当初の計画通り「7年前後になりそう」(同)。予想以上に太陽光パネルの発電量が多いおかげだ。
7年後からは太陽光パネルの電気は無料で使える計算になる。「太陽光発電の投資回収は10年以上だと思っていた。7年だったので驚いた」(同)と満足している。もう一つ、思いがけないメリットがあった。太陽光パネルが屋根への直射日光を遮るため、空調の効きが良くなった。夏、執務室の空調の温度設定を上げることができ、省エネにも一役買っている。
パネル価格下落 昨年秋から最安値
太陽光パネルの価格下落も投資回収を早めた要因と思われる。太陽光発電事業を展開するオリックス環境エネルギー本部事業開発部の村上洋輔副部長は「24年秋から最安値」と語る。増産によって供給過剰となった中国メーカーが値下げしたためだ。自家消費には有利な環境となっている。
オリックスは同社の負担で太陽光パネルを取り付け、発電した電気を売るPPA(電力販売契約)を企業に提供している。大企業が次々と採用し「ほとんどの大型工場の屋根は太陽光パネルが設置された」(村上副部長)状況だ。
一方で中小企業への普及は遅い。大企業が主導してサプライチェーン(供給網)を構成する中小企業に導入していくようなスキームを検討中だという。
日刊工業新聞 2025年7月18日
出典:ニュースイッチ Newswitch by 日刊工業新聞社
松木喬 Matsuki Takashi 編集局第二産業部 編集委員
リアル体験を聞けました。条件、障壁が違うと理解していますが、中小企業もハードル低く導入できるケースがありました。融資の課題として、操業が何年継続するのか、という問題があると聞きます。10年以内の投資回収で資金調達の可能性が広がれば良いです。時園製作所さんを紹介いただいた、柴田敏郎さん(中小企業診断士、柴田コンサルタンシー634)ありがとうございました。